最近よくそう思う。
今月に入って毎週末、毎日台風台風、それもすべからく災害級。静岡では鉄塔が倒れ、また街が浸水しているニュースが流れた。先週は埼玉、これは台風そのものでは無く関連した雨雲による集中豪雨が原因だそうだ。
元からこんなにひどかったのだろうか、僕が今まで住んでた地域がたまたま大丈夫だったのかもしれないが、少なくとも線状降水帯なんて言葉は聞きなれない言葉だ。一昔前はゲリラ豪雨なんていってた、夕立みたいなイメージだったが今や洪水になる災害を指している。
昔雨水対策関係の仕事をしていた際、国管理の一級河川利根川が時間100mm対応まで河川拡幅されている、利根川への支流にあたる手賀川や大津川は千葉県管轄で時間50mmまでは放流可能である。そのため支流に注ぐ雨水排水は時間50mmをmaxとし、それを超えるのであれば浸透施設を校庭などの公共空間に設置し内水氾濫を防ぐように計画していた記憶がある。
昨今の降雨状況だとどうなんだろう、3年前の台風24号では試験湛水中の八ッ場ダムも満水になり、栗橋でも限界水深ギリギリセーフ、地下のパルテノン神殿こと東京外郭放水路も大活躍。利根川下流では遊水池が機能したため、住宅街への被害は聞かなかった記憶ですが、同じ台風で長野付近は大水害に見舞われ新幹線が水没していた映像が今も記憶に残っています。
本当に日本がいわゆるスコール当たり前の内水害大国になったらどうなるのか。島国日本は大陸と違って降った雨が急速に下流に集まる。現在の雨水対策では限界がきているのかもしれない。
開発伐採により消えていった森林はもちろんのこと、市街地から消えていった田んぼ、畑にも貯水遊水機能があった。昨今の豪雨に対する切り札はこのあたりにもあるかもしれない。
気象庁の最近の降雨データと各地方整備局の河川排水想定雨量なんかを見比べてみても面白いかもしれない。今度暇な時に調査して、今の変化しつつある気象条件に行政の排水計画が追いつけているのか定量で比べてみようと思います。
とにかく他人事ではない、隣の国の話では無いのが日本の豪雨災害なので、大雨洪水警報、特別警報を注視しながら、低地にはなるべく近づかないことを心がけたいですね。
3.11の東北大震災の後は、それまで海沿いが人気だったにも関わらず不謹慎ながら内陸の地価が上がったと聞いた。
駅近など利便性が地価と直結してきたが、武蔵小杉のタワマン浸水事例もある、今一度人間が自然災害をコントロールできなかった時代、原点に帰って、浸水被害の無い丘に住居を構える時代が来るかもしれませんね。地盤もいいですし!
そんなことを思いました。今年中に関東圏の雨水対策調査します。以上。

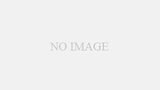

コメント